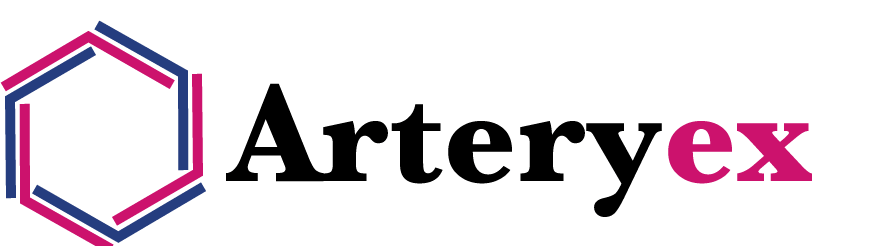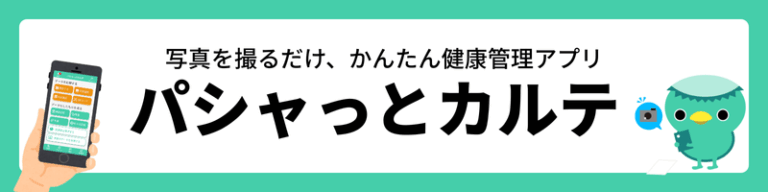自然に触れながらリフレッシュできる登山は、忙しい日常から離れ、近年新たな趣味として人気が高まっています。「山登りを始めてみたい」と考える方も多いのではないでしょうか。 一方で、「何から準備したらいいか分からない・・」「初心者で登り切れるか心配・・」など、不安を感じる方も少なくありません。しかし、事前準備をしっかり行えば誰でも簡単に山登りを楽しめます!また、自然に囲まれた静かな空間で深呼吸をして、忙しい日常から離れるだけで気分がリフレッシュされますし、登頂後の達成感や絶景を目にする瞬間の喜びを感じられるのでおすすめです♪
この記事では
- 事前準備
- 当日の流れ
- 山登りのメリット
について、山登り初心者でも安心して楽しめるよう、必要な準備から当日の流れまでを分かりやすく解説します。これを読めば、初めての山登りに必要な準備が全て整います!
目次
目次
山登り初心者でもこれだけ押さえておけば安心!事前準備のポイント
初めての山登りは不安がつきものです。「初心者だから危険なのでは?」「経験を積むまではツアーに参加すべき?」と考える方も多いでしょう。
初心者ならツアー会社が主催しているような山登りツアーに参加するのも一つの方法です。ただお金もかかりますし、自由に動いて楽しむことができないかもしれません。登山中には飲食店などがあることも多いですし、せっかくなら自分たちのペースで好きなように山登りを楽しみたいですよね。
きちんとポイントを押さえれば、自分たちだけで安全に山登りを楽しむことができます。
今回は初心者の方向けに標高1000m前後〜2000m以内(高尾山、大山、筑波山など)の山を登る場合を想定して、安心して山登りを始めるための事前準備のポイントを
- 情報収集
- おすすめのシーズン
- おすすめの服装
- 用意すべきもの
に分けてご紹介していきます。
事前準備
①計画の策定
・おすすめの季節
1000m程度の標高の低い山に登るなら、気温や天候の兼ね合いから、春(3~5月)と秋(9~11月)がおすすめです!
春秋がおすすめな理由としては、景色が綺麗なこと、また気温がちょうどよく体力面でも歩きやすい気候であることがあげられます。ちなみに、夏と冬でも登山を楽しむことはできますが、初心者の方は春と秋にスタートするのが無難でしょう。
季節ごとにポイントをまとめたので、季節選びの参考にしてみて下さい!
【春】
春には綺麗な花々が楽しめ、歩いてても楽しい季節です。
特に、4-5月は標高1000mの低山なら初心者におすすめです。ただ、春でも2000mを超える場合は雪が降っている可能性があるので注意が必要です。
【夏】
夏は一般的に、3000mほどの山を登る場合はベストシーズンと言われていますが、逆に標高が低い場合は風は少なく、蒸し蒸ししているため体力が消耗します。最近かなり暑くなっているので、初心者の方には大変かもしれません。
【秋】
秋は日没が早くなるため、登る時間の配分には気をつけてください。
紅葉が見れるので毎年人気の季節ではありますが、台風や雨で天候が不安定な傾向があるので天気予報のチェックや準備をしっかりするようにしてくださいね。
【冬】
冬でも雪が少ない地域では標高の低い山は登れますが、日が暮れるのが早く、想像以上に暗闇になってししまいます。知識や経験がないと危険なので、1回目の場合は避けるのが良いでしょう。
・天気予報の確認
天候は安全な登山の重要な要素です。前日と当日の天気を必ずチェックしましょう。
初心者の場合は当日が雨なら滑りやすくなっていますし、体が冷えやすくなってしまうのでなるべく日程を変更することがおすすめです。
また、数日前から雨の日が続いている場合も道の状況がぬかるんでいたり、地盤が緩んでいる可能性もあるため、登山計画を変更することをおすすめします。
天気を確認する際には、必ず山の麓の町の情報と、山頂の気象情報のどちらも確認するようにしましょう。街と山頂では天気の状況や気温が大幅に異なります。
・コース・バスの下調べ
地図や登山アプリでコースを事前に確認し、難所や休憩ポイントを把握しておきます。観光で行ける山を選ぶと、リフトなどがある場合がほとんどなので、そちらも合わせて確認しましょう。
また、電車で行く場合、駅から登山口までバスを利用しなくてはならない場合がほとんどです。時刻表を事前に確認し、登山計画を立てておきましょう。
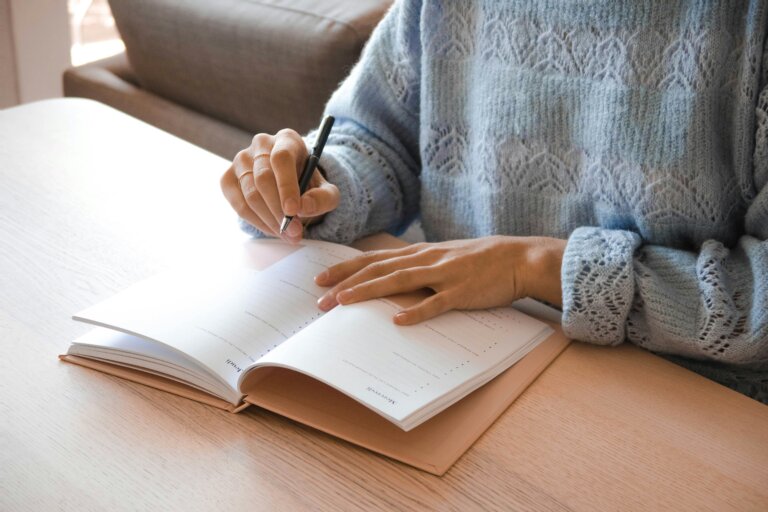
②おすすめの服装
基本的には普段着で登っても問題ありません。
初心者向けのケーブルカーやリフトがあり、道も整備されているような観光向けの山であれば、わざわざ登山用のウェアを用意する必要はなく、歩き慣れたスニーカーやズボンなど動きやすい服装を準備しましょう。
ただ、確実に押さえておかなくてはならないポイントが2つあります。
1.肌に触れるものは綿素材を使わない
山登りでかいた汗が乾かないと、体の体温を奪ってしまい、低体温症になってしまう危険性があります。
特に、綿は乾きにくいので、選ぶときは吸水性・速乾性に優れたメリノウール・ポリエステル・ナイロンなどの化学繊維のものを着るのがおすすめです。
2.雨風対策のアウターやレインウェアを用意する
山は天気が変わりやすいです。晴れの予報でも気を抜かずに、防寒具や雨具は忘れずに持っていきましょう。
また、必須ではないですが、厚手の靴下を履いていくことがおすすめです。厚手のものだと長時間歩いても靴擦れしにくくなります。
何度か登山を経験したら少しずつ登山用ウェアを用意しても良いでしょう。
初心者が買うのに最もおすすめなのが、肌に直接触れる「ベースレイヤー」です。なぜならベースのアイテムによって登山中の疲労度や快適具合が大きく左右されるためです。
吸水・速乾といった点に気をつけて選んでみてください。
③持ち物
| 持ち物 | 詳細 |
|---|---|
| スマートフォン・モバイルバッテリー | コースの検索や写真撮影など、様々な場面で必要になってきます。山登りは1日がかりになることがほとんどなので、モバイルバッテリーを持っていきましょう。 |
| バッグ | リュックなど両手が開くものがおすすめです。かなり荷物が多くなる場合は、容量や耐久性などの観点から、初心者でも購入してみるのも良いでしょう。容量は日帰りなら10~25L目安で、大体3000円台から1万円近くまで多くの種類が展開されています。 |
| 飲料水 | 登山をする場合はどの季節でも汗を書いて体の水分が減ったり、体力の消耗が激しかったりします。こまめに水分を取れるように歩きながら摂取できる飲み物を用意しておきましょう。水やスポーツドリンクなどがおすすめです。一般的に、短時間の登山(3〜5時間程度)では、一人あたり 500ml〜1L 、長時間の登山(5〜8時間以上)では一人あたり 1.5L〜3L 程度の水分補給が必要だと言われています。さらに詳しく給水量を知りたい方は、以下の式に当てはめて計算してみてください!脱水量(ml)=体重(kg)×行動時間(時間)×5 → 給水量(ml) = 脱水量 × 0.7〜0.8(https://yamap.com/magazine/41584より引用)例えば、体重50キロの場合、、脱水量=50×3×5=750なので、、給水量=750×0.7=525mlが必要ということになります!個人差はありますが、こまめに水分補給ができるように1Lのマイボトルで持ち運んだり、500mlのペットボトルは最低限でも用意しましょう。暑い季節や標高が高い場所ではさらに多めに持参したり、途中の山小屋などで買い足すことをおすすめします。ちなみに、コーヒーやお茶(ウーロン茶や緑茶など)は利尿作用があるので、登山ではおすすめできません。 |
| 雨風対策のアウター・レインウェア | 防寒性、防水性を備えたものを用意してください。山は天気が変わりやすいので、「今日は晴れだから持っていかなくても大丈夫」と油断せずに、確実に持っていきましょう。レインウェアをアウターとして使用することも可能です。折り畳み傘は登山に適していません。登山中にさすのは手が塞がってしまってバランスを崩す危険があったり、風に弱く壊れる可能性があります。どうしても用意できない場合以外は、確実に用意をしておきましょう。 |
| タオル・ティッシュ | 汗を拭くためのタオルや、汚れる場合に使えるティッシュを持っていきましょう。 |
| 常備薬・ばんそうこう | 常備薬やばんそうこう、酔い止めなど、具合が悪くなった時や靴擦れをしてしまった時のために最低限バッグに入れておきましょう。 |
| 持ち物 | 詳細 |
|---|---|
| 折り畳み傘 | 山登り中はおすすめできませんが、駅までの間で使う可能性があるため、天気が崩れやすい場合は持っていきましょう。 |
| 帽子・日焼け止め | 山は標高が高いため紫外線の影響を受けやすくなります。春や夏はツバ付きのもの、秋や冬は保温性のあるニット帽などがおすすめです。日焼け止めも持っておくと便利です。 |
| 軽食(行動食) | 片手で栄養補給できる軽食を準備すると便利です。チョコレートやエネルギーバー、ゼリー飲料などがおすすめです。休憩所やご飯を食べられる場所があることが多いので、事前に確認しておくのも良いでしょう。 |
| 虫除け | 草や花が多い山では、蚊やブヨ、マダニが発生しやすいです。効果のある成分を選び、長時間効果が持続するスプレータイプなどを活用しましょう。 |
| スマートフォン・モバイルバッテリー | コースの検索や写真撮影など、様々な場面で必要になってきます。山登りは1日がかりになることがほとんどなので、モバイルバッテリーを持っていきましょう。 |
| バッグ | リュックなど両手が開くものがおすすめです。かなり荷物が多くなる場合は、容量や耐久性などの観点から、初心者でも購入してみるのも良いでしょう。容量は日帰りなら10~25L目安で、大体3000円台から1万円近くまで多くの種類が展開されています。 |
| 飲料水 | 登山をする場合はどの季節でも汗を書いて体の水分が減ったり、体力の消耗が激しかったりします。こまめに水分を取れるように歩きながら摂取できる飲み物を用意しておきましょう。水やスポーツドリンクなどがおすすめです。一般的に、短時間の登山(3〜5時間程度)では、一人あたり 500ml〜1L 、長時間の登山(5〜8時間以上)では一人あたり 1.5L〜3L 程度の水分補給が必要だと言われています。さらに詳しく給水量を知りたい方は、以下の式に当てはめて計算してみてください!脱水量(ml)=体重(kg)×行動時間(時間)×5 → 給水量(ml) = 脱水量 × 0.7〜0.8(https://yamap.com/magazine/41584より引用)例えば、体重50キロの場合、、脱水量=50×3×5=750なので、、給水量=750×0.7=525mlが必要ということになります!個人差はありますが、こまめに水分補給ができるように1Lのマイボトルで持ち運んだり、500mlのペットボトルは最低限でも用意しましょう。暑い季節や標高が高い場所ではさらに多めに持参したり、途中の山小屋などで買い足すことをおすすめします。ちなみに、コーヒーやお茶(ウーロン茶や緑茶など)は利尿作用があるので、登山ではおすすめできません。 |
| 雨風対策のアウター・レインウェア | 防寒性、防水性を備えたものを用意してください。山は天気が変わりやすいので、「今日は晴れだから持っていかなくても大丈夫」と油断せずに、確実に持っていきましょう。レインウェアをアウターとして使用することも可能です。折り畳み傘は登山に適していません。登山中にさすのは手が塞がってしまってバランスを崩す危険があったり、風に弱く壊れる可能性があります。どうしても用意できない場合以外は、確実に用意をしておきましょう。 |
| タオル・ティッシュ | 汗を拭くためのタオルや、汚れる場合に使えるティッシュを持っていきましょう。 |
| 常備薬・ばんそうこう | 常備薬やばんそうこう、酔い止めなど、具合が悪くなった時や靴擦れをしてしまった時のために最低限バッグに入れておきましょう。 |
| 折り畳み傘 | 山登り中はおすすめできませんが、駅までの間で使う可能性があるため、天気が崩れやすい場合は持っていきましょう。 |
| 帽子・日焼け止め | 山は標高が高いため紫外線の影響を受けやすくなります。春や夏はツバ付きのもの、秋や冬は保温性のあるニット帽などがおすすめです。日焼け止めも持っておくと便利です。 |
| 軽食(行動食) | 片手で栄養補給できる軽食を準備すると便利です。チョコレートやエネルギーバー、ゼリー飲料などがおすすめです。休憩所やご飯を食べられる場所があることが多いので、事前に確認しておくのも良いでしょう。 |
| 虫除け | 草や花が多い山では、蚊やブヨ、マダニが発生しやすいです。効果のある成分を選び、長時間効果が持続するスプレータイプなどを活用しましょう。 |
山登り当日の流れは?リスクや登山後のケアを解説
事前準備をしっかり行えたら、いよいよ山登り当日!安心して登山を楽しむために、
- コース選び
- 体力を消耗しない歩き方
- 登山中の注意
- 昼食のタイミング
- 登山後の楽しみ方
に分けて、気をつけるべきポイントをお伝えします!
当日
①コース選び
標高が低く、登山道が整備された道がおすすめです。
ガイドブックやウェブサイトで難易度を確認しましょう。初めて登る人は、ロープウェイやバスがある場合はそちらも利用しながら登山を楽しみましょう。
②体力を消耗しない歩き方
登山中の体力消耗を抑えるためには、登りと下りで適切な歩き方を心がけることが重要です。登りと下りで共通して大切なのは、「足裏全体で着地」することです。つま先だけで登るとふくらはぎに負担がかかりますが、足裏全体を地面につけて歩くことで、安定性が増し、滑りにくくなります。また下りの際も膝や足首への衝撃を和らげてくれます。なるべく意識して歩くことで体力の消耗を最小限にしてくれるでしょう。
【登り】
姿勢を正す:登りでは前傾姿勢になりがちですが、上半身をまっすぐに保ち、視線を前方に向けることで呼吸が楽になり、疲労を軽減できます。
【下り】
歩幅を小さく:大きな歩幅で下ると膝への負担が増します。小さな歩幅でゆっくりと歩くことで、筋肉や関節への負担を減らせます。

③登山中の注意
・水分補給をこまめにする
水分不足は低体温症や熱中症、高山病を引き起こす原因になります。特に、雨天時は晴天時以上にルートや足元の確認などが必要になるので、栄養・水分補給を意識しないと気がつかないうちに水分・エネルギー不足になりがちです。水や行動食はすぐに取り出せるようにし、喉が乾いてなくてもこまめに水分補給を心がけてください。
・体温調節に気をつける
低体温症や熱中症にならないためには休憩の時に調整するのでなく、暑さや寒さを感じた時点で調節をすることが必要です。暑く感じたらウェアを一枚ぬぐ、逆に寒さを感じたらアウターを一枚着るなど臨機応変に対応しましょう。
④昼食のタイミング
初心者向けの短いコースであれば、山頂で昼食を楽しむのがおすすめです。山小屋ならではのグルメが楽しめるでしょう。
山頂付近で昼食を予定する場合は、事前に登山計画を立てて、山頂に到着する時間を想定します。
山頂に到着する時間が昼時より遅くなる場合、エネルギー補給のために途中で軽いスナックや行動食を摂りましょう。登山中は、エネルギー消費が激しいため、昼食前に行動食を適宜摂ると良いです。空腹になる前に早めの補給を心がけましょう。
ただ、長時間の登山では、景色の良い途中の休憩スポットで昼食を摂るのも良い選択です。山での昼食は、、1〜2時間ごとに細かく分けて小刻みに行動食(途中で食べる軽食)をとるのが一般的です。今後本格的に登山を始める際は行動食を持っていきましょう。
⑤登山後の楽しみ方
下山後の楽しみといえば、温泉やお風呂です!山の近くに温泉がある低山も多いので、ぜひ探してリフレッシュしてください。例えば、高尾山などでは駅直結で「極楽湯」という温泉があります。下山後すぐ入れるので便利ですね!少し移動し八王子駅などに行けば他にもいくつか温泉があるようです。
温泉に入ってゆっくり体を温め、血流をよくすることで筋肉の回復を早くしてくれます。次の日の筋肉痛緩和のためにおすすめです。
後日
登山の楽しさを実感し、初心者でもう一度登山に挑戦したいという方向けに山の選定基準をお伝えします。趣味としてソロ登山もおすすめです!
- 日帰りで行ける山である
- 標高差が700m以下、歩行時間が5時間以内と比較的少ない、初心者でも挑戦しやすい
- 日帰りで登れる
- 登山口の近くに駅があり立地が良い
- ケーブルカーなど、コースの選択肢が沢山ある
例えば、関東に住んでいる方であれば、以下のような山がおすすめです!
1.高尾山(東京都)
標高599m、駅から徒歩5分で着きます。新宿から約50分と近く、登山道が複数あるので初心者に人気です。ケーブルカーも利用可能です。山頂からは富士山を望むことができます。
2.大山(神奈川県)
標高1252m、ケーブルカーを利用すれば 山頂まで比較的短時間で登れるので、ファミリーや初心者に人気です。ただ、最寄りの伊勢原駅からケーブルの駅までは路線バスで約30分かかります。
3.金時山(神奈川県)
標高1212m、箱根エリアの山で、山頂からの富士山の眺望が素晴らしいです。箱根湯本駅からから登山口までバスで25分程度、初心者でも登りやすいコースが整っており、整備された山道で往復3時間程度で登れます。
4.筑波山(茨城県)
標高877m 東京から高速バスで行けば約1時間〜1時間半で筑波山まで行けます。
男体山・女体山という二つの山頂があり、ロープウェイやケーブルカーを使えば手軽に楽しめます。
なお、つくばTXつくば駅から登山口まではバスで30~40分かかります。乗り継ぎに気をつけましょう。
山登りはメリットが沢山あります!
健康面や精神面など以下の3つの理由から趣味として始めるのにおすすめです!まずは初心者向けのコースからチャレンジしてみてください!
①健康維持ができる
山登りは全身を使う運動で、体力の向上や病気予防に役立ちます。例えば、筋トレと有酸素運動の両方の効果を兼ね備えており、太ももやお尻などの筋肉を鍛えながら脂肪燃焼も促進します。さらに、基礎代謝が上がるため、太りにくい体質を作ることが可能です。
また、登山中にかく汗は新陳代謝を活性化し、美肌効果も期待できます。登山専用のウェアを着ることで汗をかくことの不快感も軽減されます。健康的な生活を送りたい方に、登山はぴったりの趣味です。
②リフレッシュができる
山登りは心の健康にも良い影響を与えます。運動がメンタルヘルスの改善に有効であることは多くの研究で示されていますが、自然との触れ合いや新鮮な空気は、さらにその効果を高めるそうです。
登山ではストレス解消だけでなく、リラクゼーション効果も得られるため、心身のリフレッシュに最適です。
③仲間ができる
登山を通じて新しい仲間を作ることも可能です。例えば、山岳会という登山好きが集まるコミュニティに参加すれば、登山経験の豊富な人からアドバイスをもらえたり、登山技術を学べる講習会に参加できたりします。また、ツアー登山では、プロのガイドと一緒に安全に楽しむことができ、同じ趣味を持つ仲間と出会うチャンスも増えます。
地元のツアーに参加すれば、近くで一緒に登山を楽しめる仲間が見つかるかもしれません。最近では登山アプリやSNSなどで気軽に仲間を見つけることもできます。

まとめー山登りで健康な体づくりをしよう!ー
いかがでしたでしょうか?ここまで山登り初心者向けに、登山のポイントを解説してきました。
まとめると・・
- 初心者でもポイントを押さえれば自分たちだけで安全に山登りを楽しめる
- 事前準備のポイント:情報収集、春と秋がおすすめ、服装は普段着でも問題ない
- 当日のポイント:コースを選ぶ、足裏全体で着地をする、水分補給や体温調節をこまめにする
- 登山は健康維持、リフレッシュ、仲間作りというメリットがある
ということになります。
登山は身体面でも精神面でも健康に良いので、健康が気になる方の新しい趣味としておすすめです。運動を続けることで、肥満対策になったり病気の予防になるでしょう。
健康が気になる方は、まず毎日の体重や体温の記録から始めていきましょう。毎日記録するものなので、スマホアプリで管理をすることがおすすめです。おすすめのアプリは「パシャっとカルテ」です。日々の記録を登録するとグラフで見れるだけでなく、プロのトレーナーに健康相談をすることもできます!これらを活用して自分の健康管理をしてみてくださいね!
【パシャっとカルテのおすすめポイント】
- 毎日の体重や血圧、体温の数値を記録でき、自動でグラフ化してくれる
- 自分の健康情報を一括で管理できる
- 健康診断結果や病院の診察結果を、写真を撮るだけでデータ化してくれ、毎年の比較ができる
- スマホ一つで持ち運べるので、自分の健康データをすぐに医師に提示できる
パシャっとカルテ登録はこちらから